大菅病院について

■開業
名古屋大学を卒業し、外科学を専攻していた大菅三郎は柳橋あたりで開業しました。しかし戦争による焼失。失意の中、この大門に部屋を間借りする形で再開したのが、大菅病院の始まりです。法人の設立は、昭和27年4月25日に届けられています。大門と言えば「遊廓」。名古屋駅から西を見れば、女郎街の町並みだけが見えたと聞いています。そんな中にできた病院。救急のサイレンが聞こえれば見物客が賑わい、手術室に運び込まれる様子は、当時のちょっとした名物だったようです。もともと軍医だった大菅一郎はかっぷくが良く、大きな声は威勢良く病院に響いていました。お腹の外科が専門でしたが、外傷がおおかったこともあり骨折もみていたようです。
■その後
その後、東京は渋谷に渋谷病院、熱海には熱海温泉病院を設立。渋谷と名古屋で救急処置を受け、熱海の温泉にゆったりつかりながらリハビリというスタイルはなかなか好評でした。時は流れ、熱海温泉病院は売却。渋谷病院も閉鎖し、貸しビルへ建て替え。名古屋の長く続いた木造の建物も限界になり、平成元年には今の鉄筋の建物へと変わりました。建物は新しくなったものの、以前のような活気を帯びてくるのは少し時間がたってからでした。
■近況
昭和52年から働きはじめ、平成6年に院長となった大菅志郎。そして慶應時代の級友、坂文種報徳会病院整形外科教授、故関恒夫先生が陰ひなたに病院を支えてくださり、今の基礎が出来上がりました。そして平成13年、わたし大菅健嗣が院長となりました。
院長略歴

■地域医療額教室
平成8年に医師になった私は、大学病院研修中に抱いた「大学でしか研究が行われていないのはおかしい。医療のほとんどは大学以外でおこなわれている。地域に根ざした病院や診療所の医療を少しでも研究し、良い医療を行いたい」という思いを実現すべく、栃木県にある自治医科大学地域医療学教室に入局しました。ここは無医村に医師を派遣しつつ、より良い医療を提供するために研究・教育をしている一風変わったところでした。患者さんの苦しみを共感することから始まり、それを何とかしたいという思いから、最善の医療を模索することを教えてくれました。
■家庭医から整形外科へ
最先端の大学医療と過疎の診療所医療には、大きな差がありました。しかし、どちらも大切な医療です。私は病気を診るという視点と、人を見るという視点がともに大切であることを知りました。 院長となったとき私はあらためて「自分の専門」について考えました。その時まで、私の専門は「内科」あるいは「総合診療科」と呼ばれていました。私としては「消化器とか循環器とか臓器で区切れない、私は《あなた》という人間の専門家でありたい」という思いに近い「家庭医」という言葉が好きでした。 しかし、これを専門として掲げてもなかなか理解していただけない。私はやむなく「院長」とだけ名乗ることにしました。それでも専門を聞かれたときは「内科と整形外科」と答えることにしています。内科学会、整形外科学会に属し、両専門家に負けぬよう勉強と研修を続けています。
理念

私は毎年、この理念というものを言葉にしてみています。問いかけだけではなく、何らか解る形にしなくては、人には伝わらないと考えたためです。
今の答えは、
「患者さんのため、スタッフのため、地域のため、何ができるかを問いかけ続ける」
患者さんのためにできることは何か。
スタッフのためにできることは何か。
地域のためにできること何か。
それを問いかけ続ける先に、目指すものがあるのではないか。
明確な完成形があるのではなく、一つ一つ問いかけ続け、改善を続けていった先に、何か真理のようなものに少しでも近づこう、というのが今の答えです。
救急、整形外科、リハビリ、地域

当院は、「救急、整形外科、リハビリ、地域」の4つを医療の軸としております。
■救急
当院は、昔より救急を医療の軸の一つとして掲げています。現在、年間2500台以上の救急車の受け入れをしております。また、24時間365日、いつでも医療を受けられるよう体制を整えています。また当院では検査、治療が困難となった場合にも、適切に高度医療機関へ紹介させていただきます。
■整形外科
救急に力を入れているため、当院は外傷患者さんを数多く受け入れております。そのため、整形外科に力を入れ、ほぼ連日手術ができる体制を整えております。上肢や下肢の骨折に対して、できるだけ早く、適切に処置を行い、リハビリへつなげていきます。
■リハビリ
入院のリハビリ、外来のリハビリ、また介護保険を用いた通所のリハビリと訪問のリハビリ。途切れのないリハビリを提供するため、各種リハビリの体制を整えております。整形外科術後の患者さんや、脳梗塞などの麻痺に対して、今ある状態から少しでも改善できるよう、頑張っております。
■地域
近隣のクリニック、介護施設、接骨院さんなどの医療関係との連携を大切にし、ゲートキーパー・バックアップ病院として機能させ、地域の方が安心してくられる街づくりに協力していきたいと思っています。

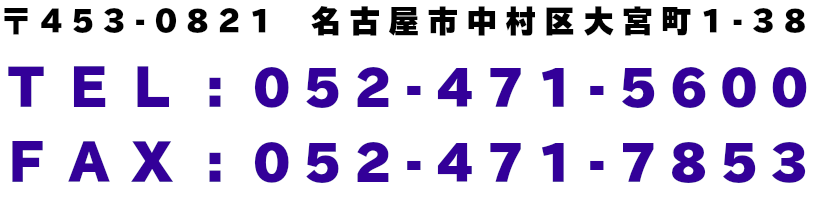
 ホーム
ホーム